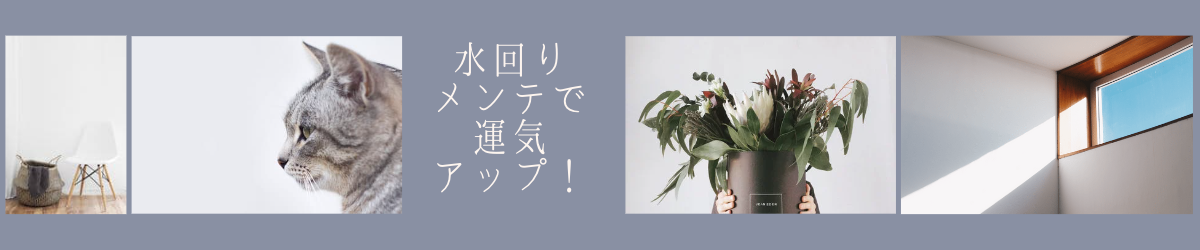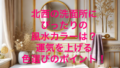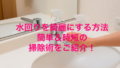水回りのコーティングを自分でやってみたいけど、「本当に素人でもできるの?」「失敗したらどうしよう」と不安に思っていませんか?
実は、コツさえ押さえれば、水回りのコーティングは自分で行うことができ、しかもプロ並みの仕上がりも目指せます。
この記事では、「水回り」「コーティング」「自分で」をキーワードに、初めての方でも失敗しないやり方や、使うべき道具、注意点までをわかりやすく紹介します。
- 水回りを自分でコーティングする方法と手順
- 初心者が失敗しやすいポイントと対策
- コーティングを長持ちさせる掃除とメンテ術
陰陽五行説について
風水と密接な関係がある、「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」について知っていると、この記事をより理解することができます。
これは中国の古代思想で、宇宙の法則、自然界と人間の関係を説明するための理論で、大きく分けて「陰陽」と「五行」の要素に基づいています。そのうちの「五行」についてご説明します。
「木(もく) 、火(か) 、土(ど) 、金(きん) 、水(すい)」の関連性については、人間関係や日常生活の意外な場面で繋がっているので、ぜひ読んでみてくださいね!
陰陽五行説「木、火、土、金、水」の特徴〜相生(そうしょう)〜
こちらは良い関係(メリット)についてです。
木が燃えて火を生じ、火が燃えたあとは土が生じ、土からなる山には鉱物(金)が生じ、金は水を生じ、水は木を成長させる、というように、順番に相手を強め、生む影響をもたらしお互いに助け合う関係を築いています。
陰陽五行説「木、火、土、金、水」の特徴〜相剋(そうこく)〜
こちらは悪い関係(デメリット)についてです。
木は土の養分を奪って抑制し、火の熱は金を溶かして抑制し、土は水をせき止めて抑制し、金は刃物として木を切り倒して抑制し、水は火を消して抑制するという、お互いが対立し合って運気を低げる関係となっています。
陰陽五行説は「色や季節や方角」に関係がある?
五行説とは、すべての物事が5つの元素から成り立ち、それらの元素が特定の法則に従って影響し合い、変化と循環を繰り返すという考え方です。
色や季節や方角など自然に関することから、政治や経済、また医学など、生活に関することにも用いられるようになりました。
そして余談ですが、五臓では、肝は木、心は火、脾は土、肺は金、腎は水とつながっています。
以上のように風水が深い関わりのある「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」を知っていることで、周囲の環境が変わり、運気アップにもつながっていくのです。
水回りのコーティングは自分でできる!初心者でも失敗しない基本手順
自宅の水回り、特にシンクや洗面台の汚れやくすみが気になってきた方におすすめなのが、コーティング作業を自分で行う方法です。
プロに頼むと費用がかさむこともありますが、最近では初心者向けのアイテムも充実しており、自宅でも気軽に施工できるようになっています。
ここでは、水回りのコーティングを自分でやるための基本的な流れについて、わかりやすく解説していきます。
自分でできる水回りコーティングの対象とは?

水回りコーティングの対象となる場所は主に以下の通りです。
- キッチンのシンク・蛇口周辺
- 洗面台・浴室のカウンター
- トイレの便座・手洗い場
これらの部分は日常的に水や汚れにさらされやすく、劣化やカビの原因にもなりやすい場所です。
コーティングを施すことで、撥水性・防汚性が高まり、日々の掃除が格段に楽になります。
特に最近は「ガラス系コーティング剤」や「フッ素系コーティング剤」など、市販でも高性能な製品が手に入るため、自分でチャレンジする方が増えています。
注意点としては、対象物の素材がコーティングに適しているかを事前に確認することが大切です。
陶器・ステンレス・人工大理石などは問題ありませんが、木材や塗装が弱い素材は不適な場合がありますので、パッケージ記載の使用可能素材を必ずチェックしましょう。
自宅にある道具で始められるかチェックしよう!
水回りのコーティング作業には、特別な専門機材は必要ありません。実は、自宅にある掃除道具を活用するだけで十分に対応可能です。
まずは、以下のようなアイテムが家にあるかを確認してみましょう。
- ゴム手袋:手荒れ防止や安全のために必須。
- 中性洗剤:事前の油汚れや水垢の除去に使用。
- 柔らかいスポンジや布:コーティング剤を塗布・拭き取りするために必要。
- キッチンペーパーやマイクロファイバークロス:仕上げの拭き上げに使うと便利。
これらの基本的な道具に加えて、市販のコーティング剤(ガラス系・フッ素系)を準備すればすぐに始められます。
ポイントは「表面をきれいにしてからコーティングすること」です。汚れや油分が残っていると、コーティングがうまく定着せず効果が半減してしまうため、事前の清掃は念入りに行いましょう。
もしマイクロファイバークロスや無水エタノールなどがあれば、さらに施工精度がアップします。これらは100均でも手に入るので、ぜひ準備しておきたいですね。
施工前にやるべき下準備とは?
水回りコーティングで最も重要な工程のひとつが、施工前の下準備です。これをおろそかにすると、どんなに高性能なコーティング剤を使っても効果が十分に発揮されません。
まずは以下のステップで、しっかりと下地処理を行いましょう。
① 汚れ・水垢・カビの除去
中性洗剤やクレンザー、メラミンスポンジなどを使い、シンクや洗面台に付着した水垢、ヌメリ、カビなどの汚れを徹底的に落とします。
特に水回りは目に見えない油汚れや石鹸カスが付いていることが多いため、細かい部分まで丁寧に掃除しましょう。
② 表面の乾燥
掃除が終わったら、水分をしっかり拭き取り、完全に乾燥させることが重要です。
湿気が残っていると、コーティング剤が弾かれてしまったり、ムラになる原因になります。
自然乾燥を待つか、マイクロファイバークロスやドライヤーを使って早く乾燥させると良いでしょう。
③ アルコール拭きで仕上げ
最終仕上げとして、無水エタノールを布に染み込ませて拭き上げると、表面の微細な油分も除去できます。
これにより、コーティング剤の密着力が高まり、より長持ちする仕上がりになります。
この下準備がしっかりできていれば、初心者でも驚くほどきれいに施工できます。作業の前に30分ほど時間を取って丁寧に行いましょう。
実際のコーティング作業の流れとポイント
下準備が完了したら、いよいよコーティング作業本番です。初心者の方でも安心して実践できるように、流れとコツをわかりやすく解説します。
① コーティング剤を適量取り出す
市販のコーティング剤にはスプレータイプや液体タイプがあります。使用説明書をよく読んで、適量をスポンジや専用クロスに取りましょう。
つけすぎはムラの原因になるので、「少なめに伸ばす」イメージが大切です。
② 薄く均一に塗り広げる
対象の面に向かって、円を描くように優しく塗り広げていきます。特にシンクのフチや蛇口周辺など、細かい部分もしっかりと。
厚塗りを避け、なるべく均一に仕上げることが美しい見た目と効果を長持ちさせるコツです。
③ 指定時間だけ乾燥させる
塗布後は製品に記載された乾燥時間をしっかり守ってください。
触ってもベタつかない程度に乾くまで放置するのが基本です。この乾燥時間を短縮しようとすると、仕上がりに悪影響を与えるので要注意です。
④ 仕上げの拭き上げ
乾燥後は、マイクロファイバークロスなどでやさしく拭き上げることで、ムラを取り除き、ツヤを引き出せます。
この仕上げ工程を丁寧に行うかどうかで、見た目にも差が出ます。時間を惜しまず、丁寧に行いましょう。
一度施工すれば、約3〜6か月ほど効果が持続する製品も多く、定期的なメンテナンスだけでピカピカの状態を維持することが可能です。
初心者でも使いやすい市販のコーティング剤はこれ!
「たくさん種類があってどれを選べばいいかわからない…」という方のために、初心者でも使いやすく、口コミ評価も高い市販のコーティング剤をいくつかご紹介します。
① カインズ「ガラス系コーティング剤」
ホームセンターで手軽に購入できるカインズのガラス系コーティング剤は、撥水性が高く、耐久性にも優れています。
スプレーして拭くだけなので、初めての方でも迷うことなく使えます。キッチンや洗面所の陶器・ステンレス素材に最適です。
② リンレイ「ウルトラハードコーティング剤」
洗浄力の強い製品で知られるリンレイのコーティング剤は、撥水効果+防汚効果が高く、プロ仕様に近い仕上がりが期待できます。
少し本格的にやってみたい方や、汚れが気になっている場所におすすめです。
③ 100均でも買える!「コーティングスプレー(フッ素系)」
実はダイソーやセリアなどの100円ショップにも、フッ素系の簡易コーティングスプレーが販売されています。
耐久性はやや劣るものの、試しにやってみたい・コストを抑えたいという方にはぴったり。使い切り感覚で使えるので失敗も少なくて安心です。
いずれの製品も、使用前に「対応素材」と「使用不可な場所」を必ず確認することが大切です。
まずは一か所だけ試して、仕上がりを確認してから本格的に施工すると、安心して進められますよ。
手袋・スポンジ・クロス…揃えるべき基本道具
市販のコーティング剤を購入するだけでは準備万端とは言えません。作業効率や仕上がりを左右するのが、使用する道具です。
ここでは、水回りのコーティングを自分で行う際に揃えておきたい基本の道具を紹介します。
① ゴム手袋・ビニール手袋
コーティング剤には化学成分が含まれていることが多いため、手荒れ防止や安全対策として、必ず手袋を装着しましょう。
細かい作業がしやすいフィット感のある手袋がおすすめです。
② スポンジ・コーティング専用パッド
コーティング剤を塗布する際には、柔らかいスポンジや専用パッドを使用します。
研磨剤入りのスポンジは傷をつける恐れがあるためNGです。スポンジは新品か、コーティング専用のものを使いましょう。
③ マイクロファイバークロス
仕上げの拭き取りや乾拭きには、繊維が細かく傷をつけにくいマイクロファイバークロスが最適です。
乾燥後のムラ取りにも活躍するため、最低2枚は用意しておくと安心です。
④ 無水エタノール(仕上げ拭き用)
施工前後の最終仕上げに、無水エタノールを使って油分を取り除くと、コーティングの定着力がアップします。
ドラッグストアやホームセンターで手に入り、用途も広いので1本持っておくと便利です。
これらの道具はすべて100均やホームセンターで手軽に揃います。事前に準備しておくことで、スムーズに作業を進められ、仕上がりの質もグッと向上します。
よくある失敗例とその原因
水回りのコーティングは手軽に始められる一方で、「うまくいかなかった…」という失敗例も少なくありません。
ここでは、初心者がやりがちな失敗とその原因を解説します。あらかじめ知っておくことで、同じミスを避けることができます。
① 汚れや油分をしっかり落とさずに施工
もっとも多い失敗が「下地処理不足」です。
見た目にはきれいに見えても、油分や水垢が残っていると、コーティング剤が弾かれて密着せず、ムラや剥がれの原因になります。
② 塗布量が多すぎる(厚塗り)
「たくさん塗れば長持ちする」と思いがちですが、厚塗りは逆効果です。
乾燥不良やムラになりやすく、仕上がりが白っぽくなってしまうケースもあります。基本は「薄く・均一に」が鉄則です。
③ 乾燥時間を守らず触ってしまう
施工後すぐに触ったり、水をかけてしまったりすると、定着前のコーティングが崩れてしまいます。
製品ごとの「乾燥時間」は必ず守ることが成功のポイントです。
④ 対象素材に合わないコーティング剤を使用
陶器やステンレスには使えても、プラスチックや塗装面には不向きな製品もあります。
コーティング剤のパッケージを確認せずに使用すると、表面が変色したり、滑りすぎて危険なこともあります。
これらの失敗を防ぐためには、「使用前の確認」と「丁寧な施工」が何より大切です。
湿気・乾燥・時間帯にも注意が必要!
水回りのコーティングは、「塗って乾かすだけ」と思われがちですが、施工する環境によって仕上がりが大きく左右されます。
特に重要なのが、湿気・乾燥状態・施工する時間帯です。
① 湿度が高い日は避けよう
梅雨時や雨の日は、空気中の湿気が多く、コーティング剤の乾燥に時間がかかるだけでなく、ムラや白濁の原因になることもあります。
なるべく湿度の低い晴れた日、または換気をしっかり行った室内での作業がおすすめです。
② 施工前後の「乾燥」が超重要
施工前に水分が残っていると、密着不良やコーティングのはがれの原因に。
また、施工後も表面が乾ききるまで絶対に水や湿気を触れさせないようにしましょう。
最低でも5〜6時間、できれば一晩は放置しておくと安心です。
③ おすすめの施工時間帯は「午前中」
午後に施工すると、乾燥前に夜の湿度が上がってしまうことがあります。
日光や風通しのある午前中に作業をスタートすれば、しっかり乾かすことができて成功率も高くなります。
たかが環境、されど環境。コーティングの仕上がりや耐久性に直結する要素なので、時間帯や天候にもぜひ気を配ってくださいね。
自分でやるメリットとは?コストと自由度
水回りのコーティングを「自分でやってみようかな」と思うきっかけの多くは、費用を抑えたいという気持ちからではないでしょうか?
ここでは、プロに依頼せずに自分でコーティングするメリットを整理してみましょう。
① 圧倒的にコストが安い
プロに依頼すると、キッチンや洗面台のコーティングで1〜3万円程度の費用がかかります。
それに対して自分でやる場合は、コーティング剤+道具で1,000〜3,000円前後に収まることがほとんど。
少しの手間で数万円の節約ができるのは、大きな魅力ですよね。
② 好きなタイミングで施工できる
自分でやる場合、わざわざ予約を取る必要がなく、思い立ったときにすぐ始められるのがメリット。
天気のいい日や、掃除のついでなど、自分のペースで無理なく進められるのは、忙しい人にとって大きな利点です。
③ 細かい場所も自分で調整できる
プロにお願いすると、時間やコストの都合で「ざっくり」になりがちな場所も、自分なら気になる部分をとことん丁寧に仕上げられるのも魅力です。
特に蛇口の根本や、シンクの角などの細部は、自分でやることで納得いく仕上がりが目指せます。
もちろん多少の手間はかかりますが、コスト・自由度・達成感の3つがそろうのは「自分でやる派」ならではのメリットです。
プロに依頼する場合の費用と仕上がりの違い
「やっぱりプロに頼んだ方が安心なのでは?」と感じている方もいるかもしれません。
確かに、プロに依頼することで得られるメリットは多く、仕上がりにも大きな違いがあります。
① 費用の相場はどれくらい?
プロの施工費用は、シンクや洗面台などの水回り1箇所で1〜3万円前後が一般的です。
施工面積や素材、使用するコーティング剤によっては5万円以上かかるケースもあります。
一見高く感じますが、高品質な業務用コーティング剤+専用機器による仕上げなので、耐久性と防汚効果は格段に上です。
② 仕上がりのレベルはやはり違う
プロは汚れの除去から下地処理、コーティングの均一な塗布まで、全工程を最適な方法で行ってくれるため、ムラが少なく、見た目にも美しい仕上がりになります。
また、施工後の保証がついている業者も多く、トラブル時の対応も安心です。
③ 時間と労力を節約できる
自分でやる場合は準備・施工・乾燥まで数時間〜半日かかりますが、プロに頼めば短時間で完了し、手間も省けます。
忙しい方や高齢者の方、小さなお子さんがいる家庭などでは、安全・時短の観点からプロの利用も検討の価値ありです。
コストを抑えて自分でやるか、安心とクオリティ重視でプロに任せるか。ライフスタイルや予算に合わせて選ぶのがベストですね。
日々の掃除で気をつけるべきこと
せっかく丁寧に水回りをコーティングしたのに、毎日の掃除の仕方によっては効果が短くなってしまうこともあります。
コーティングを長持ちさせるには、「やさしく、適切に掃除すること」が重要です。
① 研磨剤入りの洗剤やスポンジはNG
クレンザーやメラミンスポンジなど、研磨効果のある道具はコーティング層を削ってしまう可能性があります。
中性洗剤と柔らかいスポンジを使い、優しくこすり洗いするのが基本です。
② 強いアルカリ洗剤や酸性洗剤は避ける
一部の強力洗剤は、コーティング成分を化学的に分解してしまうことがあります。
特にガラス系・フッ素系のコーティングは薬品に弱い場合もあるため、普段使いの洗剤は「中性」と明記されているものを選びましょう。
③ 濡れたまま放置せず、こまめに水気を拭き取る
水滴が残ると、水垢やカルキ汚れの原因になります。使用後はマイクロファイバークロスなどでサッと水気を拭き取る習慣をつけると、コーティング層が劣化しにくくなります。
日々のちょっとした気配りが、コーティングの持ちを大きく左右します。「汚れを落とす」より「汚れを防ぐ」意識で掃除すると、いつでもピカピカの水回りをキープできますよ。
定期的なメンテナンスのタイミングとは?
水回りのコーティングは一度施工すれば永久に効果が続くわけではありません。日々の使用や掃除によって徐々に摩耗していくため、定期的なメンテナンスが必要です。
① コーティングの寿命はどれくらい?
市販のコーティング剤の効果持続期間は約3か月〜6か月が目安です。
使用頻度や掃除方法によって短くなることもあるため、「撥水効果が弱くなったな」と感じたら再施工を検討しましょう。
② 再コーティングのタイミング
以下のような状態が見られたら、再コーティングのサインです。
- 水が弾かず、ベタッと広がるようになった
- くすみや汚れが付きやすくなった
- 表面にツヤがなくなってきた
これらの変化が出てきたタイミングで、軽く掃除してから再度コーティングを塗布すればOKです。
③ 季節の変わり目や大掃除のタイミングでルーチン化
3か月に1度を目安に、季節ごとの節目や大掃除のタイミングに合わせると、忘れずにメンテナンスができます。
継続的に手をかけてあげることで、新品同様の美しさと快適さを長く保てますよ。
【まとめ】水回りのコーティングを自分で行う前に知っておくべきこと
水回りのコーティングは、専門業者に依頼しなくても、適切な道具と正しい手順さえ知っていれば、自分でキレイに施工できる作業です。
費用を抑えつつ、汚れにくく清潔な状態を保てるという点で、多くの家庭で注目されています。
ただし、成功のカギを握るのは、以下の3つです:
- 徹底した下準備(掃除・乾燥)
- 丁寧でムラのない塗布
- 施工後の正しいメンテナンスと掃除方法
また、湿気や気温、時間帯などの施工環境にも注意を払うことで、より高い効果が得られます。
初めてでも失敗しにくい市販のコーティング剤を活用し、まずは一部分からチャレンジしてみるのもおすすめです。
慣れてきたら、シンクや洗面台、浴室など、家中の水回りを自分の手でピカピカに保つことも夢ではありません。
ぜひこの記事を参考に、水回りのコーティングDIYを始めてみてくださいね!
- 水回りのコーティングは自分でも簡単にできる
- シンク・洗面台などが施工対象
- 準備は掃除・乾燥・道具の確認が重要
- 市販のガラス・フッ素系剤が初心者におすすめ
- 厚塗りや乾燥不足は失敗の原因
- 施工は湿度や時間帯にも注意が必要
- 自分でやればコストを大きく抑えられる
- プロは高品質・高耐久で時短が魅力
- 日々の掃除は中性洗剤とやさしい拭き取りが基本
- 効果が薄れたら3〜6か月ごとに再施工が理想
\ジャンル別ブログ紹介/
管理人が運営している、他の人気ブログはこちらから↓
- ▶ アニメ・ドラマ好きな方へ(生活に役立つ情報も!)
- ▶ 運気を整えたいあなたに(水回り×風水で家の運気アップ)
- ▶ 猫との暮らしを楽しみたい方へ(猫の気持ちと便利グッズを紹介)